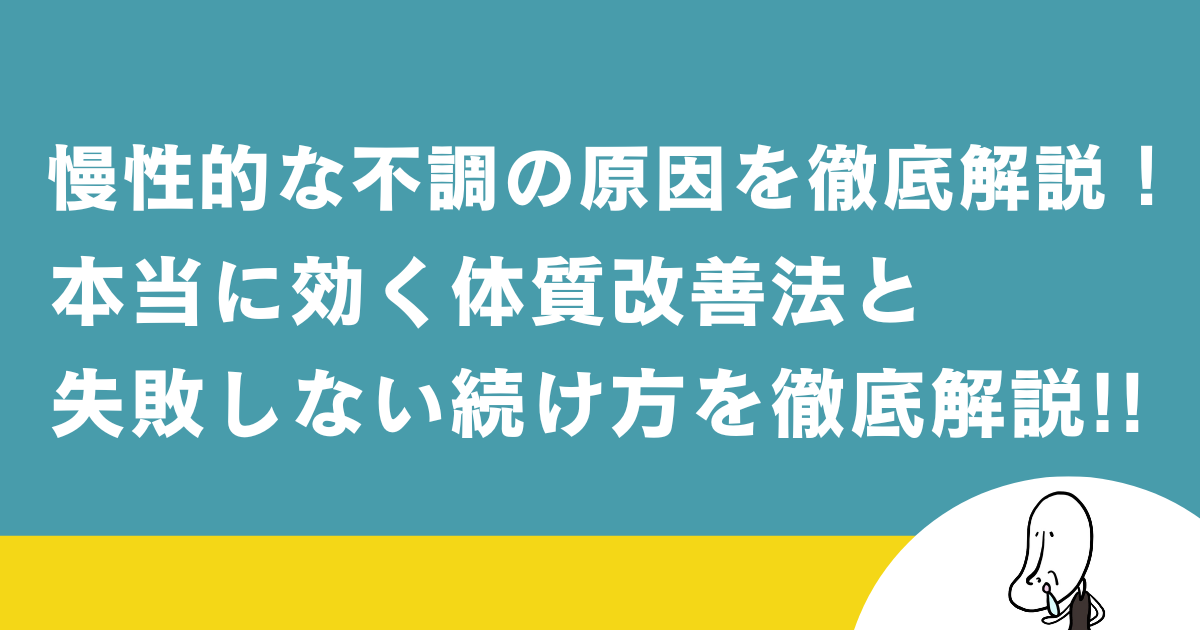- Contents
この記事のゴール:「不調の原因を理解すること」と「体質改善継続のコツ」を知る
「最近、体の調子が優れない」
「風邪をひきやすくなった」
「便秘や冷え性、肌荒れがひどい」
「慢性的な鼻炎に悩んでいる」
「朝起きた時の後鼻漏がつらい…」
これらの症状は、完全な風邪や病気ではないため病院に行くほどでもなく、また周りに相談もしづらく、自分でなんとかしようとネットで情報を見て色々試してみるけど、どうにもならず疲れが溜まっていってしまう、、、
どうすれば良いのか、もうお手上げ!!🥲という方に向けてこの記事を書きます。
SALIVA Labo(サリーバ・ラボ)では最も効果的かつ継続可能な方法(経済的にも精神的にも)を、実際の体験と様々なエビデンスを基に解説していきます。
最後まで読んで頂ければ、悩み続けた不調の原因とその改善方法について理解できます。
また、体質改善におすすめの商品やサービスも紹介しているので是非参考にしてください!
不調の根本原因:「糖化」と「酸化」
「糖化」と「酸化」はどちらもさまざまな病気の要因となる現象です(老化2トップと名付けちゃいましょう)。「糖化=体の焦げつき」「酸化=体の錆びつき」とか言われたりしますが、あんまりピンときませんね。
結論から言うと、糖化も酸化も両方、
細胞を傷つけ、細胞の機能を低下させてしまう
のが問題です。
両者ともに、細胞を傷つける方法(つまりメカニズム)がちょっと違うだけで、「細胞を傷つけ万病の原因となる」ということは同じです。
糖化は細胞を「炎症」させて傷つけるから「コゲ」で、酸化は文字通り細胞を「酸化」して傷つけるから「サビ」なんでしょうね。それぞれの細かな説明はいったん後回しにして、まずは「細胞が傷つく」ということはどういうことなのか?について触れていきます。
「細胞が傷つく」ことによる悪影響
「細胞」とは、カラダの組織(内蔵や血管、神経など)を作るものです。1個1個の細胞がブロックのように積み重なって、内臓や血管、神経ができているイメージ。
その1つ1つの細胞が傷つく、ということはつまり、内臓や血管、神経が傷つく、ということ。傷ついた内臓や血管、神経は、それぞれが持っている機能を低下させてしまいます。
じゃあ内臓や血管、神経の「機能」ってなんなの?というと、
例えば「自律神経」は、免疫をコントロールする白血球の数や働きを調整します。「内臓や血管」は、カラダの新陳代謝を支え、免疫機能を含む生命維持活動を担う機能を持ちます。
つまりどの組織も、「免疫機能」という、我々のカラダが正常に動くための役割を果たしていて、その機能が低下するということは、カラダ全体の免疫力低下に繋がる、ということです。つまり、
「糖化」or「酸化」による細胞の損傷
→細胞の機能低下
→カラダの各組織(内臓・神経)の機能低下
→カラダ全体の機能低下(主に免疫機能)
という負のスパイラルに陥って、もろもろの不調を招いてしまう、ということです。このスパイラルをもう少し詳しく説明すると、下記となります。
・傷ついた細胞の機能低下&老化
傷ついた細胞は、ちゃんと栄養を取り込めない&老廃物をうまく排出できないというWパンチで細胞内はゴミの山状態に。そうなった細胞は正常な新陳代謝=「古い細胞を排除し、新しい細胞を生成するサイクル」が正しく機能せず、老化を進行させる。
・カラダ全体の免疫力が低下
細胞が機能不全に陥ることで、たくさんの細胞から作られる内蔵・血管・神経などの働きも低下します。免疫をコントロールする白血球の数や働きを調整する自律神経や、免疫機能を含む生命維持活動を担う内臓や血管の機能低下がカラダ全体の免疫力低下に繋がり、万病の原因となるのです。
繰り返しますが、細胞の損傷(炎症や酸化)→細胞の機能低下→内臓や神経の機能低下→体全体の免疫力低下
というスパイラルに陥って、体の不調を招いてしまう、ということです。
つまり、ほとんどのカラダの不調(⬇︎)はこの「細胞の損傷」が原因なんじゃねーか?ってことです。
■ 生活習慣病系
高血圧/糖尿病/脂質異常症/動脈硬化/心筋梗塞/狭心症/脳卒中/脳梗塞/COPD(肺気腫)/一部のガン(大腸・胃・肺など)
■ アレルギー・免疫系
花粉症/アトピー性皮膚炎/喘息/アレルギー性鼻炎/食物アレルギー/自己免疫疾患(橋本病、SLE、関節リウマチ など)
■ 難病・神経系
パーキンソン病/アルツハイマー型認知症/潰瘍性大腸炎/クローン病/関節リウマチ/SLE/メニエール病/多発性硬化症/筋萎縮性側索硬化症(ALS)
例えば、「酸化」で細胞を傷つける大悪役が「活性酸素」というヤツなんですが、
「多くの病気が、活性酸素と直接的あるいは間接的な関わりを持っている」
「全疾患の90%以上に活性酸素が関与している」
と言うお医者さんや研究者も多いんです。
でもそれは、この細胞が損傷することによって体内で起きるメカニズム(細胞損傷→細胞機能低下→カラダ組織の機能低下)を知れば、元を正せばほとんどの病気の原因がこれなんだな、という結論に至るのは当然かと思います。
とうことは!!
逆に、「糖化や酸化を防ぐこと」が、もろもろのカラダの不調を治していくことに繋がる、ということもご理解頂けると思います。
次の章から、じゃあどうすれば糖化や酸化が防げるのか、どうすれば体質改善を継続して行うことができるか?について、10年体質改善に取り組んできた経験をもとにお話しします。
①糖化:体のコゲつき
※2025年4月に、日本最大の化学の学会「日本化学会」で体内の「糖化」進行を可視化させた大分市の女子中学生が話題になりましたが、それだけこの「糖化」が注目を集めているということですね。
糖化とは、「食事や間食で摂取した過剰な糖と体内のタンパク質や脂質が結合し、老化物質であるAGEs(終末糖化産物)を生成し細胞を傷つける現象」です。このAGEsを生成する結合は、体温によってゆっくりと進むため「体のコゲ」とも呼ばれます。
※特に食後の血糖値が急激に上昇するタイミングで起こりやすい
生成されたAGEsは体内に蓄積され、細胞に炎症を引き起こします(つまり細胞を傷つけるということ)。こうして傷ついた細胞はその機能を低下させ、我々のカラダを上記の負のスパイラルに落とし込んでいきます。まとめると、
①糖化によりAGEsが蓄積
②蓄積したAGEsが細胞を傷つける(炎症させる)
③細胞が傷つく=カラダの組織(内蔵・血管・神経)も傷ついて機能低下&老化
④免疫が下がりあらゆる不調に繋がる
ということ。ここまで読んで頂いて、もう一度赤字だけ読んで頂けると幸いです。筆者があえて赤字にしているキーワードには全て、「糖」という文字が入っていますね。
そう、つまり、「諸悪の根源は脂質やタンパク質ではなく「糖」なんすよ!」
って言いたかったんす。
「低脂肪」を売りにした食品が未だにスーパーでよく見かけますが、実はそこじゃないんですよと。(これはまた別記事でお話しますが、脂肪は摂った方が良い)
要はなるべく、甘いものを避けて血糖値を上げない食生活をする!ということがかなり大事になってくるということなんです!!
・・・・・・が!!
筆者はこの内容を読んだり書いたりすると、甘いものを食べない(特に加工された白砂糖が使われている製品)を頑張ろうと思えるんだけど、しばらくこの内容に触れない・読まない日が続くとどーしても甘いものに手が伸びてしまったりします。(昨日も昼食後、芋けんぴとおかき食ってしまった・・)
難しいですよね、甘いものをやめるって。じゃあどうすれば良いの?ということについて、10年間体質改善に取り組んできた筆者ならではの工夫がありますので、後述します。
その前に、「糖化」と並んで老化を促進させる「酸化」というものについて説明させてください🙏
酸化:体のサビつき
次は「酸化」について。我々のカラダは、呼吸によって酸素を取り込み、エネルギーを作り出します。しかし、取り込んだ酸素の一部は活性酸素という物質に変化します。初めて聞いた言葉だ、という方は、まずはこの「活性酸素」という言葉をご認知ください。
💡「活性酸素」の役割※読み飛ばしOK
体内で異物(細菌やウイルスなど)を攻撃し、排除します。
これをわかりやすく言い換えると、細胞が互いに情報(シグナル)をやり取りする際に、その情報を運ぶ機能を持つ、ということです。例えば、免疫細胞が病原体と戦う際に、活性酸素を放出して他の免疫細胞に攻撃を促したり、細胞の増殖や分化を制御したりします。
活性酸素の増加による悪影響
体内に過剰な活性酸素を発生させる原因
活性酸素が増加する原因は、紫外線、喫煙、アルコール、食品添加物、ストレス、過度の運動、大気汚染などが挙げられます。この中で、特に避けたいものをピックアップして説明します。
- 喫煙:タバコの煙には活性酸素を発生させる物質が含まれており、動脈硬化の原因となる酸化LDLを生成。
アルコール:アルコールを過剰に摂取すると、肝臓での分解時に活性酸素が発生。
この2つは「カラダに良くないもの」という認識は古くからあるものの、なかなか、やめられるものではありませんよね。とりあえず、なぜ「カラダに良くないのか」という事実だけでも認識しておくことが大事かと思います。 - トランス脂肪酸を含む加工食品
章の冒頭では「食品添加物」と書きましたが、特に「トランス脂肪酸」を含む加工食品は避けた方が良いです。トランス脂肪酸は、マーガリンやショートニングなどの加工食品、そして牛肉や乳製品などの天然由来の食品に含まれています。
避けたい加工食品- マーガリン、ショートニング、ファットスプレッド:
常温で液体の植物油を固形化するために水素添加されることがあり、この過程でトランス脂肪酸が生成されます.
- パン、ケーキ、ドーナツなどの洋菓子:
マーガリンやショートニングを原材料として使用している場合が多く、トランス脂肪酸が含まれる可能性がある.
- 揚げ物:
揚げ油として使用される油脂にトランス脂肪酸が含まれる場合や、揚げ物に使用される油が繰り返し使用されることでトランス脂肪酸が増加することがある.¥
- インスタントラーメン:
麺やスープの油にトランス脂肪酸が含まれている場合がある.
天然由来の食品:- 牛肉、羊肉(反すう動物:一度飲み込んだ食べ物を口の中に戻し再び噛む動物)胃の中で微生物によって生成された天然のトランス脂肪酸が含まれる.牛乳、バター、チーズ:
これらの乳製品にも、反すう動物の体内微生物の働きにより生成された、天然のトランス脂肪酸が含まれています.
その他:- 植物油脂:一部の植物油脂にも、微量のトランス脂肪酸が含まれていることがあります.
- ストレス:
ストレスを受けると、血管が収縮し、血行が悪くなります。血行が戻る際に活性酸素が発生し、酸化を促進します。
- 過度の運動:
激しい運動は、呼吸量が増加し、活性酸素の発生を促す.
これも、特にアスリートの皆さんにはぜひ知っておいて欲しい項目です。かつての自分も、サッカーをしていたので、「運動はけっこうしているから大丈夫だ」と思っていたんですが、「過度な運動」はカラダにとって逆効果、ということを知ってからは、激しいトレーニングを取り入れる頻度を調整するようになりました。 - 大気汚染:
排気ガスに含まれる有害物質が、活性酸素を増加させることがある.
- 加齢:加齢により活性酸素を分解する能力が低下し活性酸素が蓄積しやすくなる.紫外線:紫外線は皮膚細胞で活性酸素を生成し、シミやシワの原因に.
次の章から、どうすれば体質改善を継続して行うことができるか?について、10年体質改善に取り組んできた経験をもとにお話しします。
体質改善を続けるコツ
結論から言うと、「自分がストレスにならない方法を見つけること」が1番大切です。
上記の活性酸素の項でも挙げましたが、「強いストレス」というものは、甘いものをめちゃくちゃ食べて体内で起こる「糖化」に匹敵するくらい身体にとって有害であるから、です。(体感としてなんとなくわかりますよね)
どう有害なのかと言うと、「ストレス」を受けると身体をメンテナンスするための大事なビタミンたちが消費されちゃう、ということなんです。
これを科学的に説明すると、こうなります。(疲れてる人は飛ばしても🆗)
ストレスを受けると、
①体内のエネルギー消費量➕分泌されるホルモンの合成量、が増加し、ビタミン(特にB群・C)などの栄養素が多く消費される。
②さらに、ストレスは抗酸化機能の低下を招き、ビタミンC・Eなどの抗酸化ビタミンの不足を引き起こす可能性がある。
難しい言葉が多く出てきたけど、要はストレスによってビタミンが消費されて、「酸化」を防ぐための抗酸化機能も低下しちゃいますよ、ということですね。
「こうしなければいけない」とか、「これはしてはいけない」と思ってしまうことをできるだけ減らすことが、体質改善へのストレスを軽減させる上で最も大事なことだと思います。
別記事で、ストレスなく体質改善を進めるための食品、アイテム、工夫(主に食べ方)を紹介してたいと思います。
体質改善はじめの第一歩
今まで全く「体質改善」ということを意識せず、好きなものを食べ、好きな生活スタイル(夜更かし多めなど)を送ってきた、という人もいれば、いろいろと試してきたけどなかなか効果が実感できず続かなかった、と言う人もいると思います。
どんな人にとっても、まず大切なことは「身体にとっての事実」を知ることで、その事実をもとに日々の選択をしていくことが大事です。どんな選択をすれば良いか?というところで、下記に、一般的に言われている体質改善アプローチ方法をご紹介します。
王道的な体質改善アプローチ5選(やることリストに加える体質改善)
食生活の質を向上させる(例:加工食品を避け、発酵食品・旬の野菜を摂る)
運動習慣(有酸素運動を20分以上、週に2回以上)
ストレスマネジメント(瞑想・呼吸・自然との接触など)
睡眠の質(十分な睡眠時間:7~8時間以上を取れているか)
サプリメントや漢方の活用(いつ、何を、どのタイミングで摂取するか)
上記が良いと言うことはなんとなく理解できますよね。でも、これを習慣として継続させることが難しいんです。なので逆に、「やらない」体質改善を紹介したいと思います。(これはこれで難しいんですが。)
「やらない」体質改善
白い加工食品(特に砂糖・小麦粉)とリノール酸を含む加工食品を食べない
※砂糖や小麦粉が入っているお菓子を食べる場合、食前に水、お酢、サラダ、フルーツなどを食べて胃腸をウォーミングアップさせる→これは「血糖値」の急激な上昇を避け、体内で「糖化」をさせないための食習慣です。砂糖やお菓子だけでなく、普通の食事でも胃腸のウオーミングアップは効果的です。特にお酢など「酸性」の飲み物を食前に飲むと、胃酸が活性化され胃の働きが良くなり、腸における吸収をスムーズにして血糖値を下げる効果があります。
白米をやめて玄米にする
※玄米がどーしても嫌な場合、白米に五穀米・キヌア・ひえ・あわなどの雑穀を入れる
→これも血糖値の上昇を避けるためです。白米は玄米を精米して作ったものですが、精米する際にたくさんの栄養素(特にビタミンB群)や食物繊維も一緒に取り除いてしまいます。
精米されたお米はほとんどが「炭水化物」なので、それをそのままダイレクトに食べてしまうと血糖値の爆上がりに繋がります。これに対して玄米は食物繊維が豊富で、白米に比べると血糖値の上昇も緩やかになります。どうしても白米が良い、と言う人は、白米と一緒に五穀米を入れたり、海苔やわかめ、ひじきなどの水溶性食物繊維を多く含む食べ物と一緒に食べる、ということでかなり血糖値の上昇を抑えることができます。
寝る前の3時間前以降は固形物を食べない
16時間食べない時間を1週間に3日取る
体質改善ってそもそも何?
- 体質改善=身体の免疫力を上げ、根本的な不調の原因を解決する(一時的な対症療法ではない)
例えば風邪をひいてしまって、39度の熱が出たらほとんどの人が病院に行くと思います。病院で3日分などの薬を処方してもらって、それを飲んで休んで熱が下がるのを待つ・・
花粉症なども、耳鼻科に行って、鼻の中を吸われて、薬をまとめて出されてそれを飲む。(薬が切れたらまた耳鼻科に)
このような、日本のほとんどの病院やクリニックで行われる治療のことを、「対症療法」といいます。対症療法という四字熟語を分解すると、「症状」に対し治療する方「法」、と言ったとこでしょうか。つまり、1つの症状のみにスポットを当て、それに即効で効く治療(多くはお薬)を施す、という治療法ですね(西洋医学では一般的にこのような方法で治療を行います)。
これに対して体質改善とは、生活習慣や食習慣を改善することで、身体が本来持つ免疫の力を上げ、そもそも「症状」に悩まされることのない状態を作っていく、ことを目的とします。
体質改善はどのくらいで効果が出るか?
体質改善の効果が出るまでの時間ですが、結論から言うと「その人による」ということです。つまり、目的や方法、個人の体質・生活習慣によって異なりますが、一般的な目安は以下の通りとなります。
| 期間 | 期待できる変化 |
|---|---|
| 1〜2週間 | ・むくみや便通の改善 ・睡眠の質の向上 ・肌荒れの軽減 |
| 1ヶ月 | ・体重や体脂肪の変化が出始める ・エネルギーレベルの向上 ・慢性疲労感の軽減 |
| 3ヶ月 | ・ホルモンバランスや代謝機能の改善 ・冷えやアレルギー症状の緩和 ・継続的な体調の安定 |
| 6ヶ月〜1年 | ・「体質が変わった」と実感できる状態へ ・病院に頼らない身体へ ・生活習慣病の予防や改善 |
あらゆることを試してもなかなか効果が出ない人もいれば、逆に、割とすぐに(早ければ1日で)効果が出る人は出ます。その人の持っている体の状態(特に腸内環境)や環境(家庭、仕事、住居、生活スタイルなど)によって、身体に起こる変化のスピードは変わりますが、
「最低でも3ヶ月は継続する」ことが、体質改善の定着には重要で、体の細胞は約3ヶ月で生まれ変わると言われています。